ヨモギ
学名:Artemisia indica var. maximowiczii
科名:キク科ヨモギ属
分類:多年草
花言葉:「幸福」「平和」「平穏」「夫婦愛」「決して離れない」
別名
よく繁殖して四方に広がることから「四方草」
春によく萌える草から「善萌草」
よく燃えることから「善燃草」
ヨモギの「ギ」は、茎のある立ち草を意味する
葉裏の毛を集めて灸に用いることから、ヤイトグサ
春に若芽を摘んで餅に入れることからモチグサ(餅草)
方言
エモギ
サシモグサ(さしも草)
サセモグサ
サセモ
タレハグサ(垂れ葉草)
モグサ
ヤキクサ(焼き草)
ヤイグサ(焼い草)
ヨゴミ
沖縄県では、近縁種のニシヨモギをフーチーパーとよんで、臭み消しや薬用、香草として使われる。
陶穀の『清異録』には「肚裏屏風」の別名がある。
北海道アイヌ語と樺太アイヌ語では、エゾヨモギ(オオヨモギ、ヤマヨモギ)を共通してノヤ(アイヌ語: noya)と呼ぶ。これは「揉み草」の意で、薬草として葉を揉み傷口に張り付けたことに由来。
採取
食用にするには初夏(6月)のころまでのやわらかい茎先を摘んで利用。
塩を少量入れた熱湯で茹でて十分に水にさらしてアク抜きする。
繊維質が強く消化が悪いため、細かく刻んだりすり潰す。
艾葉
6~8月ころ、よく生育した葉を採集して干したものを、艾葉(がいよう)という。
地上部を刈り取りよく水洗いして葉だけを摘み取り、タオルや新聞紙に挟んで水気をしっかりとる。ザルに広げて一週間ほど天日に干し、カラカラに干し上げる。
利用
浸剤(よもぎ茶)
艾葉1日量3~5グラムを約400 – 600mlの水をいれ、弱火で2分ほど煎じる。
茶こしでかすを取り除き、数回に分けて飲む。
冷めると味が落ちるため、ポットなどで保温しておく。
煎剤
艾葉1日量15グラムを約600 ccの水で半量になるまでとろ火で煮詰めた煎じ汁
ウルシ・草かぶれ、あせも、湿疹の患部に冷湿布する
歯痛、のどの痛み、扁桃炎、風邪の咳止めにうがい薬として用いる
注意
温めながら治す薬草であるので、手足がほてりやすい人や、のぼせ気味の人には禁忌

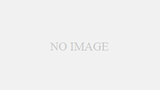
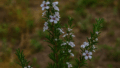
コメント